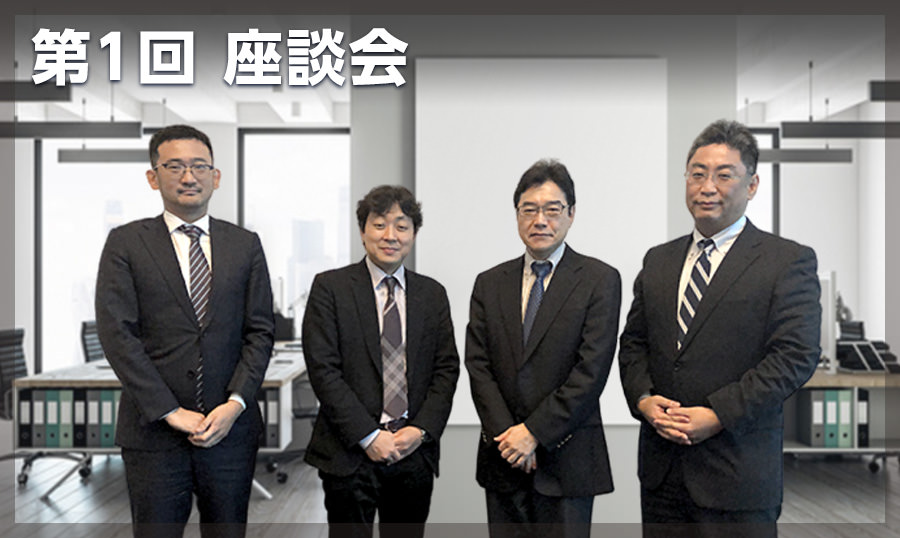第14回座談会は、肝細胞癌のTOPICSとして2024年に発表された最新のデータに基づいて、国立がん研究センター東病院 肝胆膵内 科長 池田公史 先生、近畿大学医学部 消化器内科 上嶋 一臣 先生、千葉大学医学部附属病院 消化器内科 小笠原 定久 先生、京都府立医科大学 消化器内科 森口 理久 先生にお集まりいただき、各々についてのレクチャーとディスカッションを行いました。
各領域のエキスパートによるディスカッションした内容を掲載します。
第14回座談会は、肝細胞癌のTOPICSとして2024年に発表された最新のデータに基づいて、国立がん研究センター東病院 肝胆膵内 科長 池田公史 先生、近畿大学医学部 消化器内科 上嶋 一臣 先生、千葉大学医学部附属病院 消化器内科 小笠原 定久 先生、京都府立医科大学 消化器内科 森口 理久 先生にお集まりいただき、各々についてのレクチャーとディスカッションを行いました。
第14回座談会は、肝細胞癌のTOPICSとして2024年に発表された最新のデータに基づいて、国立がん研究センター東病院 肝胆膵内 科長 池田公史 先生、近畿大学医学部 消化器内科 上嶋 一臣 先生、千葉大学医学部附属病院 消化器内科 小笠原 定久 先生、京都府立医科大学 消化器内科 森口 理久 先生にお集まりいただき、各々についてのレクチャーとディスカッションを行いました。
第14回座談会は、肝細胞癌のTOPICSとして2024年に発表された最新のデータに基づいて、国立がん研究センター東病院 肝胆膵内 科長 池田公史 先生、近畿大学医学部 消化器内科 上嶋 一臣 先生、千葉大学医学部附属病院 消化器内科 小笠原 定久 先生、京都府立医科大学 消化器内科 森口 理久 先生にお集まりいただき、各々についてのレクチャーとディスカッションを行いました。
第13回座談会は、肝細胞癌の治療「Early stage・Intermediate stage・Advanced stage」について、国立がん研究センター東病院 肝胆膵内 科長 池田公史 先生、近畿大学医学部 消化器内科 上嶋 一臣 先生、千葉大学医学部附属病院 消化器内科 小笠原 定久 先生、武蔵野赤十字病院 副院長・消化器科 部長 黒崎 雅之 先生にお集まりいただき、各々についてのレクチャーとディスカッションを行いました。
第13回座談会は、肝細胞癌の治療「Early stage・Intermediate stage・Advanced stage」について、国立がん研究センター東病院 肝胆膵内 科長 池田公史 先生、近畿大学医学部 消化器内科 上嶋 一臣 先生、千葉大学医学部附属病院 消化器内科 小笠原 定久 先生、武蔵野赤十字病院 副院長・消化器科 部長 黒崎 雅之 先生にお集まりいただき、各々についてのレクチャーとディスカッションを行いました。
第13回座談会は、肝細胞癌の治療「Early stage・Intermediate stage・Advanced stage」について、国立がん研究センター東病院 肝胆膵内 科長 池田公史 先生、近畿大学医学部 消化器内科 上嶋 一臣 先生、千葉大学医学部附属病院 消化器内科 小笠原 定久 先生、武蔵野赤十字病院 副院長・消化器科 部長 黒崎 雅之 先生にお集まりいただき、各々についてのレクチャーとディスカッションを行いました。
第12回座談会はASCO2022を終えて大腸癌の一次治療の話題をディスカッションするというテーマで、佐野病院 消化器がんセンターの小高雅人先生、静岡がんセンター 消化器内科の山﨑健太郎先生と北海道大学 消化器内科の結城敏志先生にお集まりいただきお送りいたします。第三部はASCOで発表されたCAIRO5についてご解説頂き、それを踏まえたディスカッションをしていただきました。
第12回座談会はASCO2022を終えて大腸癌の一次治療の話題をディスカッションするというテーマで、佐野病院 消化器がんセンターの小高雅人先生、静岡がんセンター 消化器内科の山﨑健太郎先生と北海道大学 消化器内科の結城敏志先生にお集まりいただきお送りいたします。第二部はASCOで発表されたTRIPLETEについてご解説頂き、それを踏まえたディスカッションをしていただきました。
第12回座談会はASCO2022を終えて大腸癌の一次治療の話題をディスカッションするというテーマで、佐野病院 消化器がんセンターの小高雅人先生、静岡がんセンター 消化器内科の山﨑健太郎先生と北海道大学 消化器内科の結城敏志先生にお集まりいただきお送りいたします。第一部はASCOで発表されたPARADIGMについてご解説頂き、それを踏まえたディスカッションをしていただきました。
肝胆膵癌の免疫療法をテーマに各分野のエキスパートの先生方にお集まり頂き、全3回シリーズでお送りする第11回座談会、第三部の今回は膵臓編です。膵癌の免疫療法の可能性について金井先生に解説いただき、それを踏まえたディスカッションをしていただきました。
肝胆膵癌の免疫療法をテーマに各分野のエキスパートの先生方にお集まり頂き、全3回シリーズでお送りする第11回座談会、第2部の今回は胆道編です。ASCO-GI 2022で発表されたTOPAZ-1試験の結果を上野先生に解説いただき、それを踏まえたディスカッションをしていただきました。
第11回座談会は肝胆膵癌の免疫療法をテーマに各分野のエキスパートの先生方にお集まり頂き、全3回シリーズでお送りします。第1回目の今回は肝臓編として、ASCO-GI 2022で発表されたHIMALAYA試験の結果をはじめとする肝細胞癌治療の最新のトピックスについて池田先生に解説いただき、それを踏まえたディスカッションをしていただきました。
ASCO 2021が先ごろ閉会しました。進行大腸癌に関する興味深い話題も数多く提供された中、ここではSTELLAR、KEYNOTE-177、TRUSTY、CHRONOSの4つの臨床試験を取り上げ、消化器癌治療の3名のスペシャリストに議論していただきました。
最後のパートではprecision oncologyについて話し合っていきます。第二部の最後に遺伝子パネル検査の話題が出ましたが、はじめに尾阪先生から、その現状と問題点を解説していただき、その後にディスカッションしたいと思います。
第二部はPARP[poly-(ADP-ribose) polymerase]阻害薬のオラパリブがテーマです。2020年12月、オラパリブに「BRCA遺伝子変異陽性の治癒切除不能な膵癌における白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法後の維持療法」の適応が追加されました。進行膵癌の一次治療後の維持療法に新たな選択肢が加わりましたが、金井先生にはその作用機序と承認の根拠となった海外第3相のPOLO試験の成績を概説していただき、その後にディスカッションしたいと思います。
膵癌の化学療法の二次治療として、2020年9月、ナノリポソーマルイリノテカンが承認され、NAPOLI-1レジメンも使用できるようになった。また、BRCA 遺伝子変異陽性の治癒切除不能な膵癌における白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法後の維持療法として、オラパリブも2020年12月に承認され、使用可能となっている。そして、遺伝子パネル検査として、Foundation One Liquidも近日、使用可能となる予定である。このように、膵癌化学療法の二次治療以降の治療戦略がホットな話題であり、3人の膵がんのエキスパートの先生に、それぞれの治療、検査について解説いただき、各施設での現状についてDiscussionしたいと思います。
ESMO VIRTUAL CONGRESS 2020(ESMO2020)で、進行胃癌の1次治療にて、CheckMate 649試験とATTRACTION-4の2つの重要な試験の結果が発表されました。今回の座談会は、沖英次先生、川上尚人先生、設楽紘平先生、朴成和先生、山口研成先生にお集まりいただき、2つの試験の結果とその解釈について議論していただきました。
TKIに続いて免疫チェックポイント阻害薬が登場し、進行HCC(肝細胞癌)の治療は大きく変わろうとしています。一方、Intermediate stage HCCに対してはどの治療法を選択したらいいのか悩まれている先生方も多いと思います。そこで本日はIntermediate stage HCCの治療戦略についてスペシャリストの先生方とディスカッションしていきたいと思います。
今回の座談会は、釼持 広知先生、坪井 正博先生、三浦 理先生、山中 竹春先生にお集まりいただき、ADAURA試験の結果とその解釈について議論していただきました。
2020年、米国臨床腫瘍学会においてJCOG0603試験の結果が発表されました。今回はエキスパートの先生方にお集まりいただき、試験から独立した立場で結果をどう解釈しているか、実地診療に与える影響をどう考えておられるかについてご意見をお伺いしたいと思います。
切除不能大腸癌の全生存期間中央値は30ヶ月を超える時代に突入し、一次治療だけでなく、二次治療以降の治療戦略が非常に重要となってきました。今回は二次治療にフォーカスを当て、実際にどのように考え治療戦略を立てているのかについてディスカッションしていただきました。
免疫チェックポイント阻害薬によって肝細胞癌治療がどう変わっていくのかを2回にわたってご紹介してきました。
シリーズ3回目の今回は、肝細胞癌を対象として現在進行中の臨床試験と、今後の展望についてお話しいただきます。
IMbrave150試験の結果に注目が集まったAtezolizumab+Bevacizumab併用療法。
シリーズ2回目の今回は、IMbrave150試験結果の解説と、それを踏まえた議論をご紹介します。
免疫チェックポイント阻害薬が、今後の肝細胞癌治療を大きく変えていくと予想される。
池田 公史 先生(国立がん研究センター東病院 肝胆膵内 科長)と上野 誠 先生(神奈川県立がんセンター 消化器内科(肝胆膵) 部長)の対談を全3回シリーズでお送りします。
その1回目として、開発状況とエビデンスを解説いただき、それを踏まえた議論をしていただきました。
ついに大腸癌治療にも本格的な免疫療法の時代がやってきた——。
Nivolumab+Ipilimumab併用療法は大腸癌治療をどう変えるのか。臨床ではそれを、どう使っていけばよいのか。
第一線で活躍する4人の先生方にNivolumab+Ipilimumab併用療法に対する期待を述べていただきました。
今回はHCC治療の第一線で活躍されている先生方にお集まりいただき、HCC治療の現状と今後の展望について、特に分子標的治療薬と免疫チェックポイント阻害剤に関する使い分けやこれらの新薬への期待について、ディスカッションしていただきました。